天竜川における時間的・空間的な生息場履歴と底生無脊椎動物の応答に関する研究
著者
- 兵藤 誠/いであ株式会社
- 高橋 真司/東北大学 工学研究科
- 竹門 康弘/大阪公立大学国際基幹教育機構
- 角 哲也/京都大学防災研究所水資源環境研究センター
- 小林 草平/京都大学防災研究所水資源環境研究センター
兵藤 誠/いであ株式会社,高橋 真司/東北大学 工学研究科,竹門 康弘/大阪公立大学国際基幹教育機構,角 哲也/京都大学防災研究所水資源環境研究センター,小林 草平/京都大学防災研究所水資源環境研究センター
天竜川における時間的・空間的な生息場履歴と底生無脊椎動物の応答に関する研究
要旨:瀬や淵,たまり,ワンドなどの生息場は,洪水や土砂の移動によって形成され,その規模や頻度に応じて創出,維持,消失する.しかし,生息場に生息する生物の時間的・空間的な変化の特性を経時的に追跡し,定量的に明らかにした研究はほとんどない.本研究では,天竜川16.0k周辺を対象に,生息場の履歴と採取調査による50種の底生動物の関係を分析し,種毎に利用している生息場の分布パターンや洪水の影響を把握した.また,底生動物の空間的・時間的な応答を把握するため,生息場寿命及び生息場齢という新しい概念を用いて,生息場寿命及び生息場齢と生物多様性の関係について考察を行った.その結果,洪水に対する底生動物の応答は,多くの種は通常の生息場から一時的に異なる水理条件の生息場に避難するように利用している可能性があることを示した.また,底生動物の種数は,洪水規模や生息場齢及び生息場齢によって多様な応答を示すことを把握し,洪水撹乱の環境下において,生息場齢が多様な生息場が存在することが底生動物の多様性を維持する上で重要で役割を果たしている可能性があることを示した.
論文本編:天竜川における時間的・空間的な生息場履歴と底生無脊椎動物の応答に関する研究(PDF)
参考情報:論文作成で使用した50種の底生動物リスト(PDF)
参考文献(50種の底生動物の基礎的特性):兵藤・竹門・角・鳥居・小林(2015)天竜川における底生無脊椎動物の生息場履歴に関する基礎的特性の把握,京都大学防災研年報第58号B.(PDF)
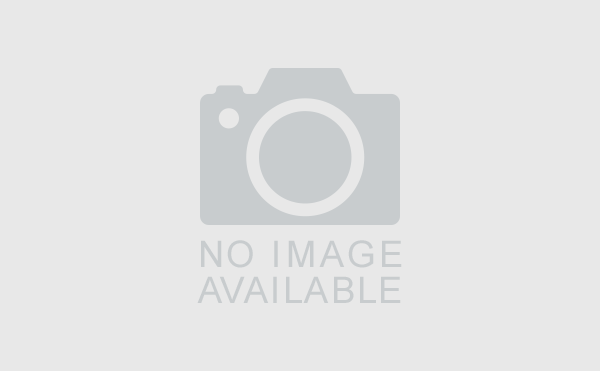

朝日航洋(株)の鈴田と申します。大変興味深い発表をありがとうございました。
洪水による擾乱が底生生物に与える影響は、空間的に散在する複数たまりの微妙な冠水条件(水位)の違いや底生生物の掃流への抵抗力、選択的な避難の有無・・・などにより生息場齢と種数の関係も複雑なのだと思いますが、なかなか面白い研究だと思いました。
スライド11において、ワンドに注目すると種数の生息場齢に伴う変化は擾乱レベルによって凸型(level2)、凹型~PE型(level3~5)と逆の結果になっており、なぜこのような結果になるのか不思議に思いました。メカニズムについて推察等が可能であればご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
朝日航洋(株)鈴田様 ご連絡いただきありがとうございます。
明確な根拠がある訳ではありません。ただ、ワンドを例にとりますと、
Level2は、水位が少し上がり澪筋とたまりが接続するくらいの撹乱の状況になります。この撹乱が生じる頻度はかなり高い状況です。短期的な変化を見ていることになります。ワンドに生息する生物は、瀬とは異なり、水位上昇で流されやすい個体が多いことが考えられます。そのため、80日くらいの箇所にピークが来ているものと思います。
Level4などは、撹乱頻度が数年に1度なので、長期的に変化を見ています。その中では、ある程度残る個体もあります。例えば掘潜型のカワヒバリガイやミツゲミズミミズ、匍匐型のオヨギダニ属(遊泳能力高い)等です。これらの種が長期長期に渡りワンドを利用できることから種数を増加させている可能性があると考えられます。
50種全種の基礎的特性を調べたものは、京都大学防災研年報にも掲載しておりますので、もしご興味があれば見ていただければ幸いです。
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/210042/1/a58b0p56.pdf
兵藤様 詳しくご説明いただき、ありがとうございました。かなり以前ですが、ヤマトシジミの生息場について、塩水楔の進入の微妙な条件で個体数が変化するのを分析したのを思い出しました。物理的なメカニズムが解明され、種数の変化予測ができるようになると面白いと思いました。
ありがとうございます。まだ課題は多いですが引き続き研究を進めていきたいと思います。よろしくお願い致します。